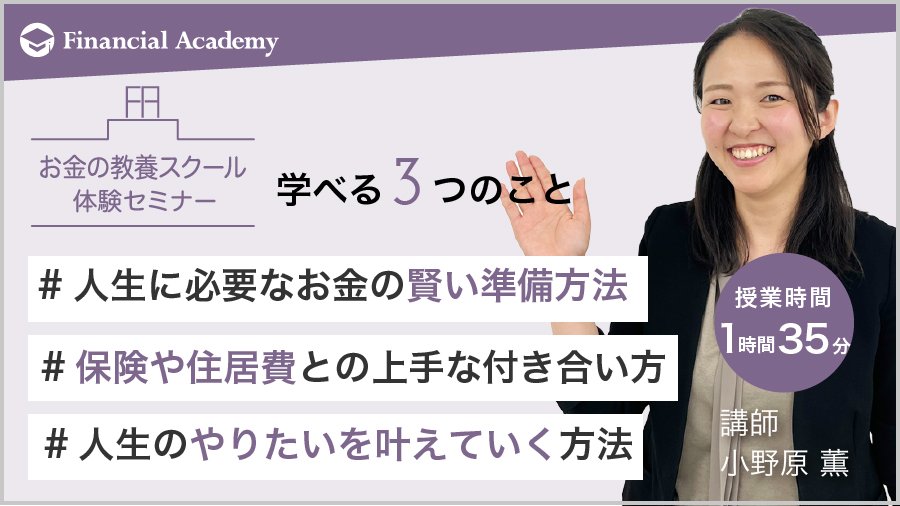年末年始は、お世話になった方へのご挨拶訪問や、来客を迎える時期です。帰省する人もいるでしょう。
その前に準備しておかねばならないのがお年玉。できるだけ出費は控えたいという本音はありつつも、金額が少なすぎて顰蹙をかったり、人間関係に悪影響を及ぼすのは避けたいもの。
そこで、お年玉の相場やマナーについて調べてみました。
何歳までお年玉をあげるべき?
お年玉は、古来、年神様に奉納していた鏡餅を氏子に分け与えていた神事が転じたものといわれています。室町時代には、お正月にお金や贈答品を渡すという風習が定着したようです。
そんなお年玉には、はっきりとした決まりや制約はありません。一般的には、学生まで、つまり高校や大学を卒業して自立するまではお年玉をあげている人が多いようです。
逆に0歳など本人がお金を理解できない年齢の子に対しては、お菓子やおもちゃをあげるという人もいるようです。
あげる側としては出費が抑えられますし、いただく側も記憶に残って、一石二鳥ですね。
親同士が親戚や友人など親しい間柄の場合は?
お年玉の金額を考えるときは、お年玉を受け取る子どもの親との関係性が重要です。
親戚や友人など親しい関係で、お互いに子どもがいるなら、親同士で金額について相談できますね。でも、自分に子どもがいない人は「いくらあげたらいい?」とは聞きづらいものです。
その場合は「年齢÷2×1,000円」という計算式を目安にすることをおすすめします。8歳なら4,000円、16歳なら8,000円ということになります。
また、親同士が金額を決めたとしても、家庭の子どもの人数が違う場合は同じでよいのか?というのも悩ましい問題です。ひとりっこと3人兄弟の家庭では、かなり差が出てしまいますね。そのせいで人間関係がギクシャクするのも避けたいもの。とは言え、不相応な金額のお年玉をあげるのも子どもの教育上いかがなものか……。そこで、図書カードや文具券など用途を限定した金券を少しプラスして渡す人もいるようです。
上司や先輩など、目上の人の子どもには?
子どもが年齢にふさわしくない大金を持つことを嫌がる親の方が多いので、目上の人の子どもだからといって上乗せする必要はありません。親の立場は関係なく、「年齢÷2×1000円」という数式を基準にすれば、失礼な印象を与えることはないでしょう。
それよりも注意したいのは、マナーです。「お年玉」には上の者が下の者に渡すという意味があるため、目上の人が意味を知っていた場合は失礼に感じるでしょう。ポチ袋には「お年賀」と書いておきましょう。さらに新札を用意したり、ポチ袋に子どもの名前をきちんと入れておくと好印象です。

最後に。手渡すときは、親がその場でお礼を言えるように親の目の前で行いましょう。
お年玉の相場やマナーなどをおさえて、家計も人間関係も笑顔の新年を迎えたいですね。