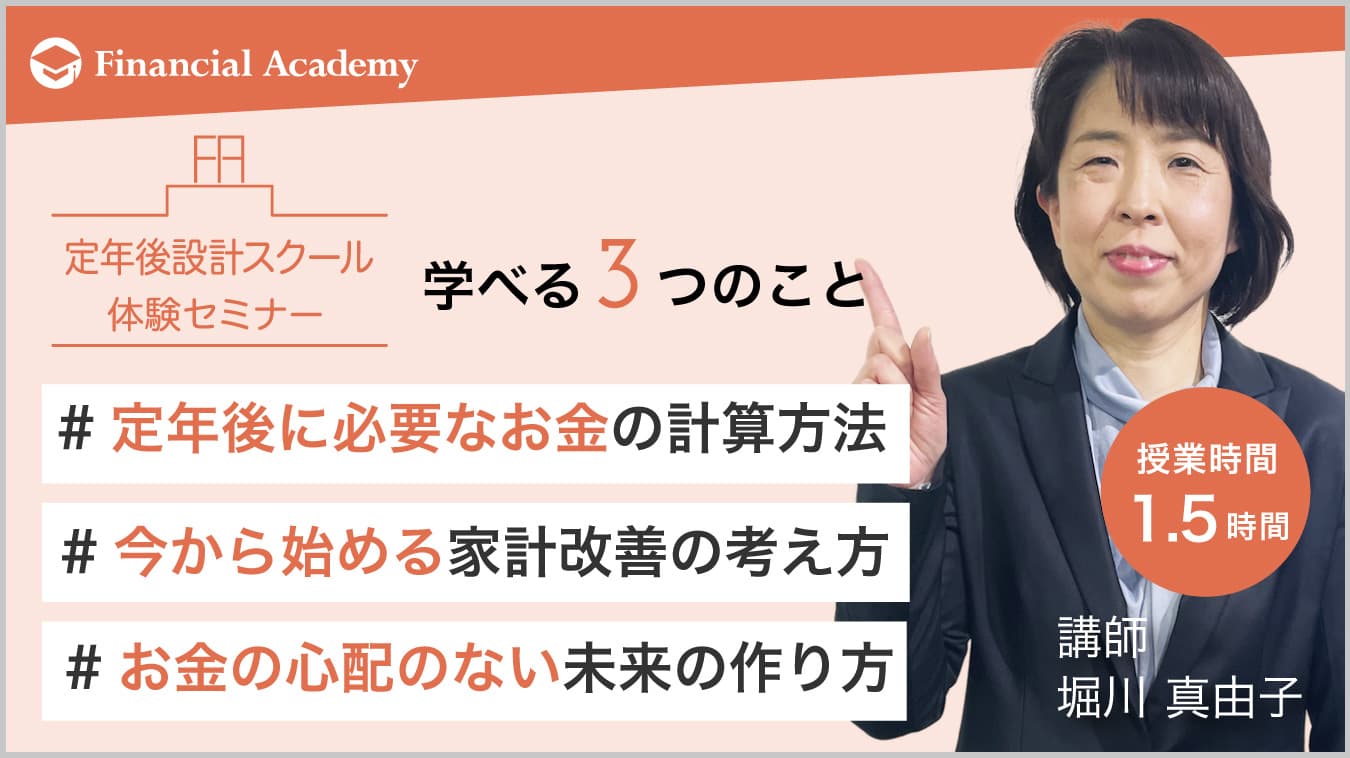相続分野において、信託の仕組みを活用した制度が広がりつつあります。高齢化が進む中、節税や遺産分割対策といったこれまでの相続対策に加え、意思判断能力が無くなった場合の財産管理をどうすべきかという課題が浮き彫りになり、その解決策の1つとして信託が注目されているのです。日本ではまだ馴染みの少ない信託の概要と、活用できる場面をご紹介します。
信託の現状
そもそも信託とは、信託法という法律に基づく財産管理の仕組みで、簡単に言うと「信頼できる第三者、又は、専門会社に財産の管理を託すこと」です。日本で信託といえば、投資信託に代表される金融商品のイメージが先行していますが、信託の制度が誕生したとされる中世のイギリスでは、家族間の財産移転を円滑に進める方法として発展してきたものです。
日本においても、2007年の信託法の改正により誰もが受託者となれる民事信託が可能となったほか、子や孫の教育資金を贈与する仕組みとして2013年4月にスタートした「教育資金贈与信託」によって、広く知られるようになりました。相続分野において伸びている「遺言代用信託」は、生存中から相続発生後にかけて自分の希望に合わせた財産管理計画を立てられる仕組みで、一般社団法人信託協会の統計による累計受託件数は、2009年度末の13件から2018年度末には169,020件にまで増えています。
相続における信託の活用例
財産管理に不安を感じ始めた高齢の親が、「日常生活以外の財産管理を子に任せたい。そして認知症などで判断能力が無くなった場合、自分が生きている間は生活費や施設への支払いをやってもらい、死亡後は残ったお金を2人の子で均等に分けてほしい」という希望をもっていたとします。死亡後の財産の分け方の話であれば遺言書でも目的を果たせますが、このように生前からの財産管理も合わせて希望する場合、信託の仕組みが有効となります。
このケースでは、財産の所有者である親を「委託者」、財産を管理する子を「受託者」として信託契約を結びます。信託契約によって財産の形式上の所有者は受託者である子に移りますが、信託財産は信託契約で設定された指示通りにしか扱えません。親が生きている間は親を「受益者」として親のために財産を使い、死亡後は相続人を受益者として財産の移転を完了する流れを親が希望する通りに作れるわけです。
家族信託のメリット
このような財産管理は、信頼関係を背景にこれまでも行われていたものです。ただ、財産管理をずさんに行い、子が自分のためにお金を使ってしまうことや、親族間で争いになった際に疑いの目を向けられてしまうなど、財産管理を行う人にとって不安も大きいものでした。また、財産管理者である「受託者」を信託銀行や信託専門会社等に任せる商事信託では、一定の費用がかかるうえ、取り扱っている専門業者も限られています。
これに対して、専門業者ではない第三者が受託者となる民事信託を活用すると、法律の裏付けがある契約によって、生前から死後にかけての財産整理を一括して行え、内容も細かく決められます。親族間でのトラブル防止が期待できるほか、費用も押さえることが可能です。なお、民事信託の中でも家族や親族の中から受託者を選ぶものを家族信託と呼びます。認知症等で意思判断能力が無くなった場合でも、自分の考えていた相続に関する希望を確実に実行する手段として、信託の活用は今後も注目が高まることでしょう。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットは大きく3つ考えられます。
まず、家族信託は財産管理の仕組みなので、本人の契約行為を代わって行うことができません。こうした身の上の手続きは、本人の判断能力が無くなった後は成年後見制度によって実現できますから、家族信託と成年後見制度の併用も検討するべきです。
また、財産の管理をする受託者が信託契約通りの管理をしてくれない不安があります。財産を預かる受託者に対しては、法律による義務や責任が定められているものの、受託者本人がそれを守らなければ意味がありません。つまり、受託者を誰に頼むのかが大きな課題となるのです。
なお、家族信託の内容が契約通り実行されているか、信託財産が守られているかをチェックする「信託監督人」を置くこともできます。そして3つ目のデメリットは、契約手続きに手間がかかる点です。家族信託を取り扱っている専門家はまだ多くありません。契約締結は当事者間だけで進めることができますが、①信託の目的を明確にして当事者を確定する、②信託契約の終了時期や承継の順番、信託期間内の報酬規程などの詳細な内容を決める、といった作業を経たうえで、③信託契約書を作成する必要があり、専門家を交えずに手続きを進めるのは困難です。信託の活用を検討する際は、信託実務を扱っている司法書士や税理士などの専門家に相談することが第一歩となるでしょう。
生涯年金を750万円多く貰える方法が自宅で学べる