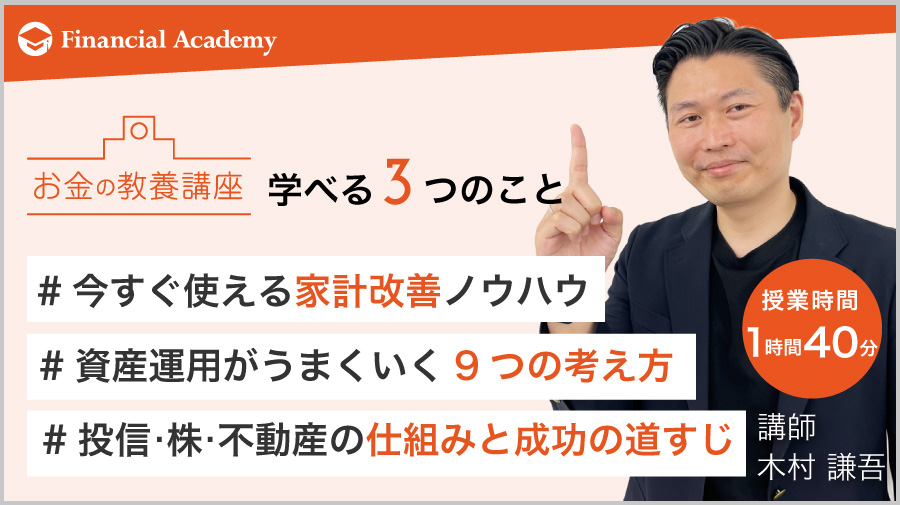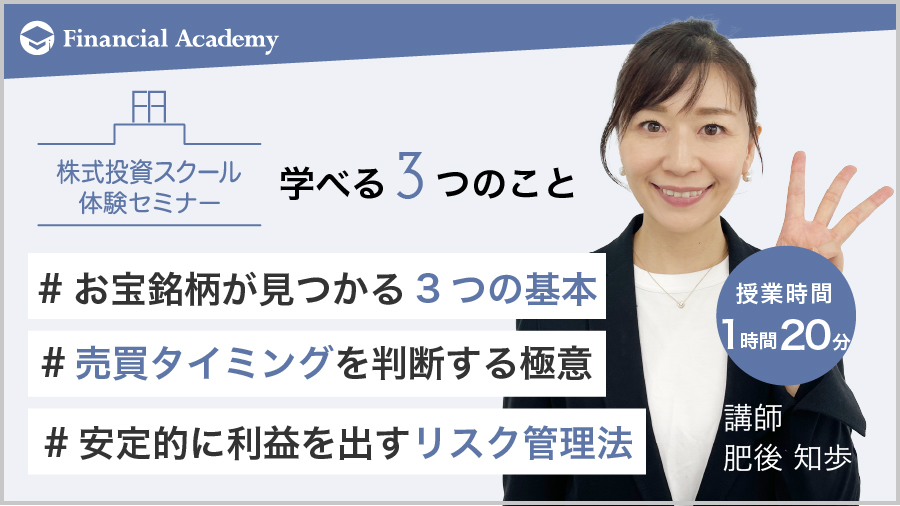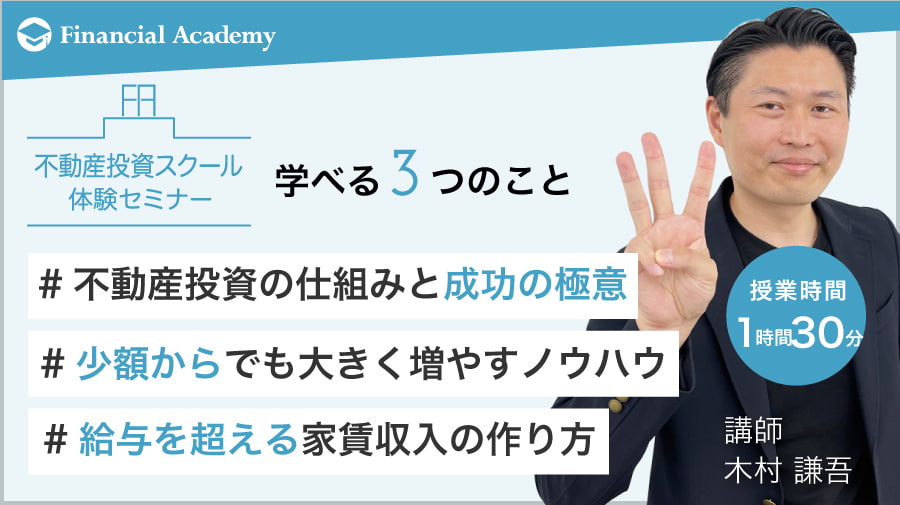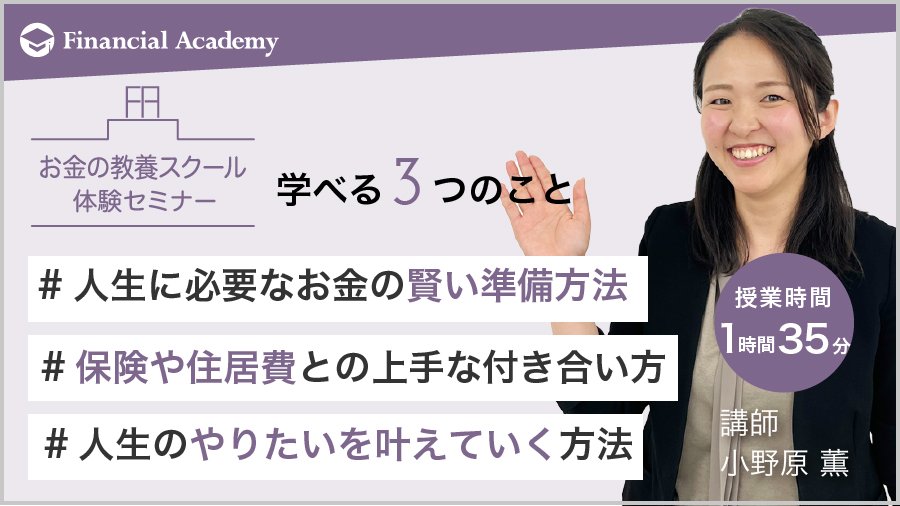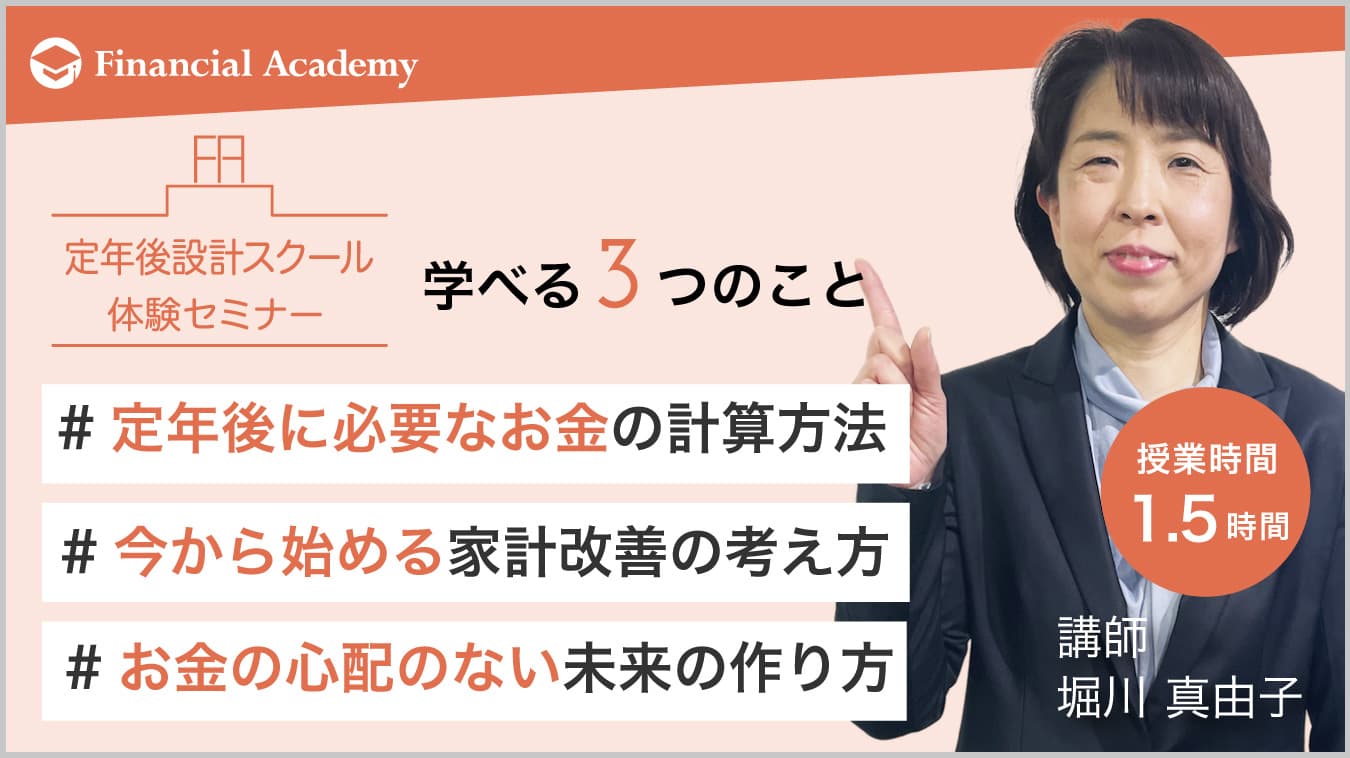国は少子化対策として、児童手当や学費の無償化制度などを実施し、子育て費用の軽減を推し進めていますが、それぞれの制度には所得制限があるもの、ないものさまざまです。そこで、所得制限があるものについて、ボーダーラインとなる年収を確認しておきましょう。
児童手当の所得制限
2024年10月分から児童手当が大幅拡充されました。
これまでは中学生以下が支給対象でしたが、この拡充で高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)も支給対象となりました。
また、児童手当は2012年6月から所得制限が設けられていましたが、今回の制度拡充で所得制限が撤廃となり、支給額は3歳未満は1万5,000円(第3子以降は3万円)、3歳以上高校生年代までは1万円(第3子以降は3万円)となっています。
児童手当の次にやってくるのが、幼児教育・保育の無償化(3~5歳児)ですが、こちらも所得制限はありません。(0~2歳児については、住民税非課税世帯のみ無償化の対象となります)
高校授業料無償化の所得制限
2010年に始まった高校授業料無償化は2014年に所得制限が加わり、名称も「高等学校等就学支援金制度」となりました。
公立高校、私立高校を問わず、高等学校等に通う所得要件を満たす世帯に就学支援金を支給する制度です。たとえば公立高校(全日制)に通う生徒の場合、年間で11万8,800円が支給され、これによって授業料が不徴収となります。
さらに、世帯年収590万円未満の世帯から私立高校等に通う場合には、就学支援金の上限額が39万6,000円まで増額します。
高等学校等就学支援金制度の所得要件には2つの目安額があります。
<世帯年収が910万円未満>
公立高校の授業料相当額にあたる11万8,800円を受給するための基準です。
ただし、年収910万円未満は目安であり、世帯構成を反映した「所得」によって判定します。計算式は以下の通りです。
「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」が、15万4,500円以上30万4,200円未満の場合
⇒年間11万8,800円の受給対象
<世帯年収が590万円未満>
子供が私立高校に進学している場合、世帯年収の基準を満たせば、就学支援金が39万6,000円まで増額しますが、その所得基準の目安です。
ただし、年収590万円未満は目安であり、世帯構成を反映した「所得」によって判定します。計算式は以下の通りです。
「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」が、15万4,500円未満で私立高校に進学している場合
⇒年間39万6,000円の受給対象
また各都道府県では、国の就学支援金制度に上乗せする形で、経済的負担を緩和する取り組みを行っています。
大学無償化の所得制限
政府は2025年から3人以上の子どもを持つ世帯について、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学等の授業料・入学金を無償とする方針を固めました。
ただし、子供を3人以上同時に扶養している間に、大学等に在学している子供が対象となります。
例えば、子供を3人(大学生2人と高校生1人)を扶養している場合は、大学生2人とも対象となります。長子が卒業等により扶養から外れ、扶養する子供の数が2人となった場合は、この「多子世帯への授業料等無償化」の支援は終了します。
まとめ
子育て費用や教育費は年々増えているのが現状です。国は子どもの養育に関わる支援制度を創設したり、改正するなどして策を講じていますが、子育て世帯すべてを支援対象とはしていません。一部の高所得世帯が外れるのは当然だとしても、所得制限となるボーダーライン付近の層は決して余裕があるわけではないと思います。特に高等学校等就学支援金制度のボーダーラインとなる年収は、層も厚く、どちらに転ぶかで数十万円の支援の差となる場合があるので、気が気ではないでしょう。
教育費にかける割合は年収が上がるほど高くなる傾向があります。教育格差が広がらないためにも、低所得者層に対する支援を厚くするのは当然のことですが、全般的に見ても子供を持つ世帯の負担は重くなっています。中間所得層が割を食うことがないような支援策を期待したいものです。