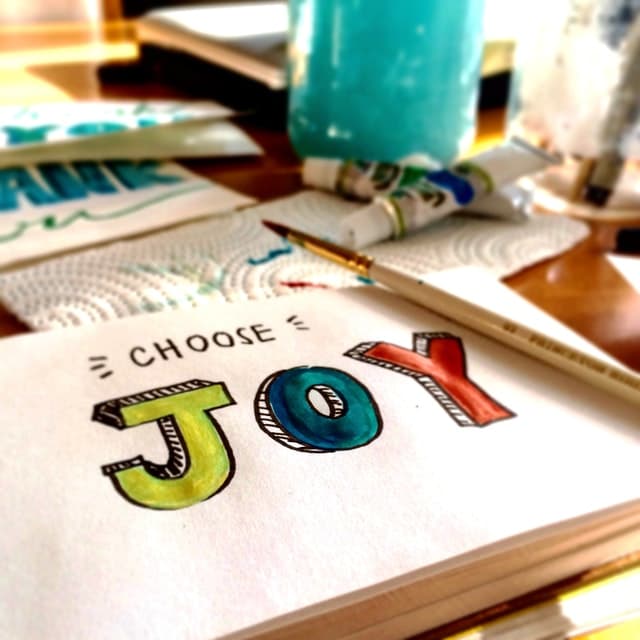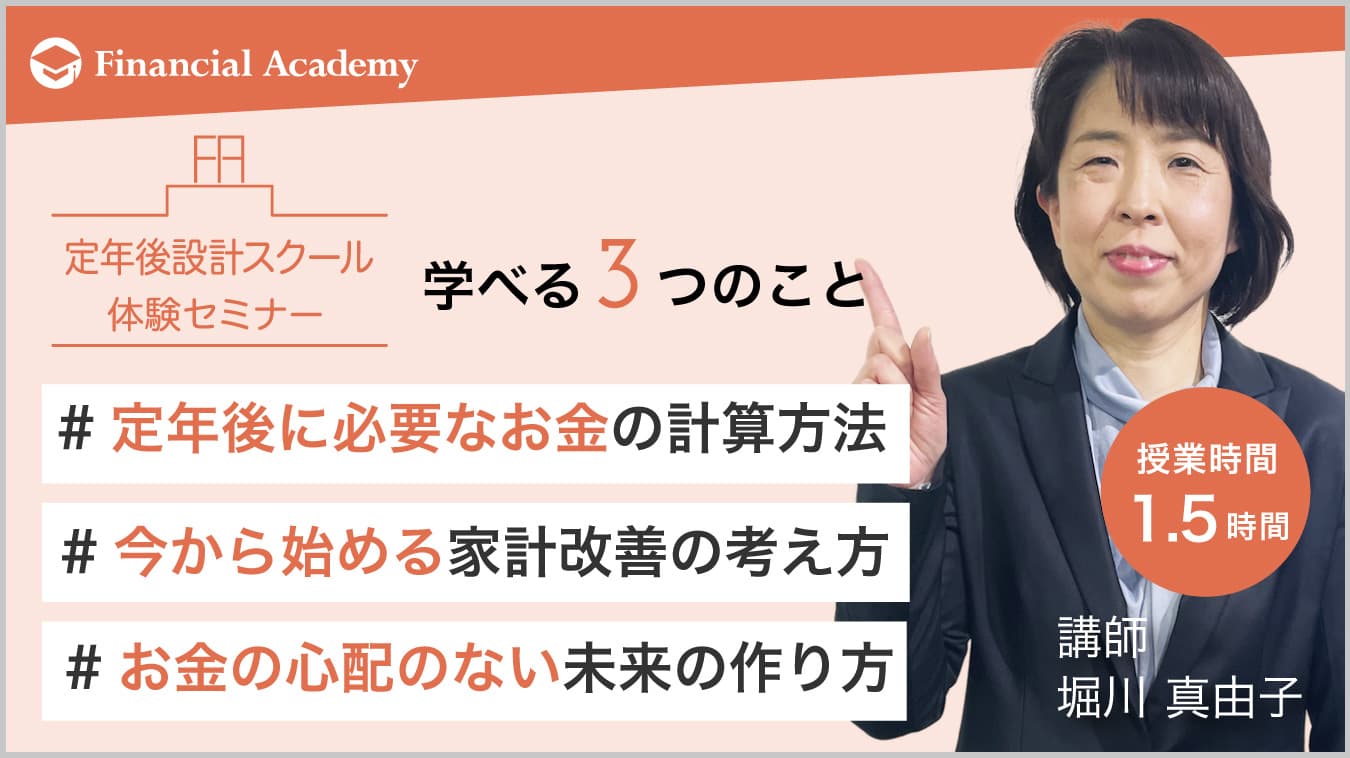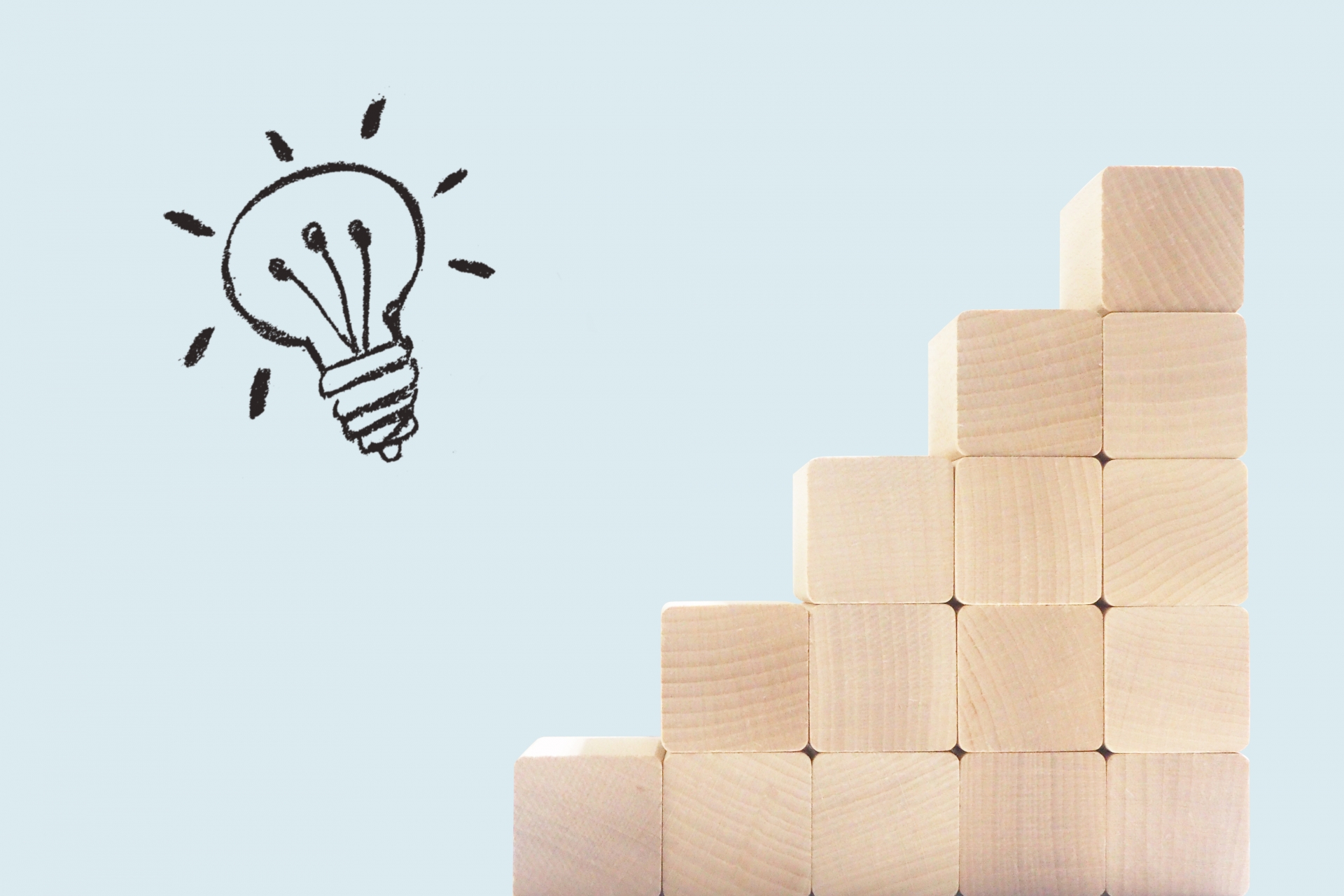忙しい日々を送っているビジネスパーソンにとっては、定年というと、寂しさを感じる反面、想像するだけでワクワクするような気持ちになることもあるかもしれません。しかし、さまざまな準備なくして定年を迎えてしまったら、思ってもみなかった現実が襲ってくることもあるようです。
遠山紘司著『もっと知りたい! 定年の楽しみ方』 より、定年後の「二度目の人生」をしっかりと楽しんでいくためのポイントをご紹介します。
退職金は焦って使わない
ひとつは「生活を安定させるための基盤」である健康と経済です。2つ目は「豊かで生きがいのある定年生活を送るための基盤」になる人間関係と趣味です。〜中略〜
50歳代の人の約80%が定年後の生活資金に不安を持っています。平均寿命が伸びたのはうれしい反面、生活予測が立てづらくなつていると思われますが、不安を抱えるだけでは解決しません。<ⅱ・1ページより引用>
平均寿命が80歳を超え、定年後の人生は実質的に見ても「二度目の人生」といえる長いものになってきています。「一度目の人生」の40年は、仕事を通じて楽しいこともそうでないこともいろいろと経験している人が多いことでしょう。
定年後の「二度目の人生」は、楽しむものと位置付けることを著者はすすめています。そのためには、下支えをしてくれる2つの基盤を固めておくことが重要なのだとか。
1つ目は「生活を安定させるための基盤」である健康と経済。そのうち、切っても切り離せないのがお金の問題でしょう。
老後の資金源は、大多数の人にとっては年金・退職金・預貯金であると推測されます。退職金は、相続で多額の遺産を受け取った人を除けば、一度に受け取るお金としては生涯で最大の額という人が多いことでしょう。その用途に対して夢が膨らみますが、退職金は年金と預貯金とともに、今後の生活を支える3本柱であることを忘れてはいけないと著者はいいます。
知識がないのに投資を始めたり、何となく海外旅行に行ったりと退職金を焦って使う必要はなく、計画が定まるまでは当面は銀行などで扱っている「退職金専用定期預金」に預けるという方法もあるのだとか。大きな金額を急に手にすると、どう使っていいのか判断が鈍ることがあります。後先のことを考えて、慎重に対応していきたいものですね。
年金・資産運用・老後の住まいなど「お金の7つの備え」がわかる無料体験学習会

定年後の人間関係は配偶者と地域がカギ
定年になってみないと見えてこないのが定年後の人間関係です。30年、40年にわたるサラリーマン時代の人間関係は職場中心ですが、定年後は自宅を中心としたものになります。〜中略〜
在職中、会社以外の人と人間関係を持たない人は多い。これは男性だけではない。近年は共働きの家庭が増え女性も同じです。フルタイムで働きながら定年を迎えた男性・女性とも地域デビューが苦手といわれます。<87・105ページより引用>
定年後の「二度目の人生」を楽しむための下支えとして、著者は2つ目に「豊かで生きがいのある定年生活を送るための基盤」である人間関係と趣味をあげています。
長年、会社組織で熱心に仕事に励んできた人ほど、仕事以外のつながりをほとんど断って生活してきた傾向もあるようです。
地域に出る前に、まず自分自身を振り返ることを著者は推奨しています。「自分は何をしたいのか、何ができるのだろうか」と考えながら、以前からしてみたいと思っていたこと、自分の知識や経験、趣味や特技・資格を書き出してみる。その中から2つか3つ程度に絞ったら、個人でやってみたいのか、既存の団体に入ってやってみたいのか、新しい団体を作ってやってみたいのかを決めるのだとか。
できれば定年後、半年以内を目途に探す時間を区切るとよいと著者はいいます。また、配偶者がいる人は、家庭での自身のあり方も重要だといえるでしょう。特に男性は、夫婦の距離感と互いを尊重する心を大切に、妻に対してべったりにならずに、一人の時間を自分自身で楽しむ力をつけておく必要があるといえそうです。

50代のうちにチェックと計画をしておく
再就職や起業といった形で迎える「二度目の人生」もあることでしょう。いずれにせよ、定年を迎えてから、「さて、どうしようか」と考え始めて右往左往していては遅いのかもしれません。現役で忙しい日々の中であっても、50代のうちにお金や人間関係に至るまで、よくチェック。しっかりと計画を立てておくことで、「二度目の人生」を自然に楽しむことができるのかもしれません。
タイトル:もっと知りたい! 定年の楽しみ方
著者:遠山紘司
発行:学文社
定価:1,620円(税込)